更新日:2025年3月28日
ここから本文です。
植えてはいけないケシの特徴
植えてはいけないけしについて
けしの仲間(ケシ属植物)は、春から夏にかけて色鮮やかで美しい大きな花を咲かせるものが多く、ガーデニングや切り花用の植物として人気があります。
しかし、けしの仲間には法律で栽培が禁止されているもの(ケシ、アツミゲシ、ハカマオニゲシ)があります。これらは、外観の特徴から園芸用のけしと区別できます。けしの仲間を正しく見分けましょう。
ケシ(ソムニフェルム種)学名:パパヴェル・ソムニフェルム
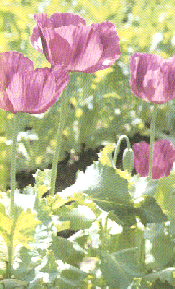
- 秋に種をまくと翌年春に、春先にまくと初夏に10cmくらいの大きな花が咲きます。
- 一重咲きの花は、花びら4枚で、色は赤、桃、紫、白などがあります。
八重咲き(多数の花びらがついたもの)もあります。 - 開花時の草丈は100~160cmくらいです。
- 葉、茎、つぼみなどの外観は、キャベツの葉のような白みを帯びた緑色をしています。
- 葉、茎、つぼみの表面には、ほとんど毛がありませんが、つぼみの下の茎(花梗)や葉の裏の主脈(葉の中心にある一番太い葉脈)には、まばらに毛がつくことがあります。
- 葉は互い違いに茎につき、上部の葉は柄がなく、茎の付け根で茎を巻き込むような形でついています。
葉の長さは10~50cm、幅は5~20cmくらいです。 - 花が終わると雌しべが発達してふくらみ、だ円または球形で、上部が平たい皿のような形をした大きな果実(けしぼうず:径3~6cm、長さ3~7cm)になります。
(注)春に種をまいたときは、草丈が1mに達しないことがあります。

八重咲きの花は、「ぼたんげし」、または「ペオニ(フラワード)ポピー」の名で園芸用に出回ることがありますので、注意が必要です。

アツミゲシ(セティゲルム種)学名:パパヴェル・セティゲルム

- 秋に種をまくと翌年の春に、春先にまくと初夏に花が咲きます。
- 花は、花びら4枚で、色は薄紫や赤があり、ソムニフェルム種よりも小形です。
- 開花期の草丈は50~100cmくらいです。
- 葉、茎、つぼみなどの外観は緑色で、よく枝別れ(分枝)します。
- ソムニフェルム種よりも毛が多く、つぼみのがく片やつぼみの下の茎(花梗)は毛で覆われています。
- 葉は互い違いに茎につき、上部の葉は柄がなく、茎の付け根で茎に巻き込むような形でついています。葉の大きさはソムニフェルム種よりも小形です。
- 果実(けしぼうず)はソムニフェルム種よりも小形です。
ハカマオニゲシ(ブラクテアツム種)学名:パパヴェル・ブラクテアツム

- 花が終わり植物が枯れた後も根が残り、翌年も同じところから芽を出します。
- 初夏に、径10cmくらいの鮮やかな深紅の大きな花を咲かせます。花びらは4?6枚で、基部に黒紫の鮮明な斑点があります。
- 花びらのすぐ真下に4~6枚のハカマ(苞葉)があります。これは、果実が出来て、果実の下の茎(果梗)が枯れるまで残り、ハカマのように見えるので「ハカマオニゲシ」の名前の由来となりました。
- 草丈は60~100cmくらいで、葉や茎全体が白く硬い毛で覆われています。
- 葉は濃緑色で、鳥の羽の様な形に深く切れ込んでいます。地面に近い部分の葉(根出葉)は、長い柄(葉柄)があり、長さは柄を含め20~25cmで密についています。
- つぼみを覆う2枚のがく片の表面には、硬く伏した(寝た)毛が多数ついています。
- 果実は、表面に毛がなく、青緑色です。
ハカマオニゲシは、「植えても良いけし」のオニゲシと、外観が非常によく似ています。
ハカマオニゲシの「鮮やかな深紅の花の色」、「花びらの基部に存在する鮮明な黒紫の斑点」、「つぼみの(がく片の表面)の伏した(寝た)硬い毛(オニゲシの毛は直立している傾向がある)」は、二種の植物を見分ける手がかりです。
*ハカマオニゲシは、「オニゲシ」あるいは「オリエンタルポピー」の名で園芸用に出回ることがありますので、注意が必要です。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています