更新日:2025年2月26日
ここから本文です。
大室古墳群の保存整備
大室古墳群について
大室古墳群は、長野市南部の松代町大室に所在する、古墳時代の5-7世紀代に築造された総数約500基の古墳群です。奇妙山から派生する3つの支脈尾根上とそれに挟まれた2つの谷部に立地し、約2.5km平方の範囲に密集して分布しています。古墳の分布状態とその地形条件などから大小5つの支群に大別され、うち大室谷支群の一部が国史跡に指定されました。
北山支群は、大星山の尾根上を中心として22基の古墳により構成されています。山頂近くに位置する18号噴は大室古墳群唯—の前方後円墳(全長56m)です。
大室谷支群は、大星山の支脈と中央支脈とに挟まれた谷部に分布し、古墳数241基を数えます。古墳の分布範囲は谷入ロの標高360mから最深部の660m地点までの総延長2kmに達し、著しく細長い帯状の分布を示しています。継続的な学術調査が実施されてきた地区であり、国史跡に指定されました。
霞城支群は、中央支脈の先端部尾根上に分布しています。大室集落を眼下に見る位置にあり、16基の古墳により構成されています。なお分布範囲に重複して中世段階に霞城が構築されたため一部の地形の改変がみられます。
北谷支群は、中央支脈と、尼厳山の支脈である金井山(標高495m)とに挟まれた谷部に位置し、古墳総数208基を数えます。支群内はさらに、谷裾の緩斜面と上部の4支谷に立地条件が細分されます。
金井山支群は、金井山の尾根上を中心として分布しています。鳥打峠周辺を含めて18基の古墳により構成されています。
大室古墳群の特徴
- 積石塚が古墳群全体の8割を占めていること。
- 日本全国で約40例しかない合掌形石室が、25基も確認されていること。
- 渡来系集団との関わりが考えられること。
- 馬の生産との関わりが考えられること。
史跡整備事業の概要
大室古墳群は、「積石塚」や「合掌形石室」の存在により、古くから学会において著名な遺跡でしたが、学術的な評価に比して一般市民の認知度は決して高くありませんでした。その理由としては、古墳群をとりまく環境が、盗掘や経年変化による崩落や風化、草木の繁茂などにより本来の姿が失われていることが第一に挙げられます。さらに、現地における公開施設を含む情報の希薄さ、交通アクセスの不便さ、便益施設の不足なども理由となっていました。
そのため、本事業は、古墳群の詳細な研究調査を実施し、その成果に基づいた保存整備を図ると共に、周辺部の情報提供施設の建設など、歴史的背景を体感できる史跡公園として整備し、広く公開・活用することをめざしています。
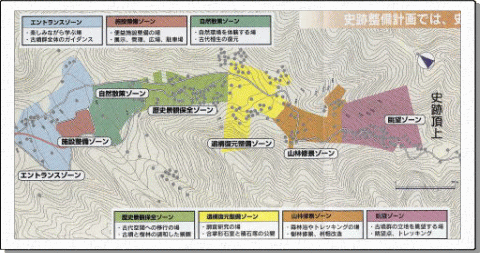
大室古墳群

合掌形石室(168号墳)
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています