ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 長野市公文書館 > 長野市公文書館-既刊本紹介 > 市誌研究ながの 第11号~第20号
更新日:2026年1月7日
ここから本文です。
市誌研究ながの 第11号~第20号
市誌研究ながの ~これまでに発行した本の紹介です~
(第11~20号)
表紙絵は「一遍上人絵詞伝」や「松代十二箇月絵巻」を使用しています。
※表中の自然、原始・古代・中世史、近世史、近現代史、旧市町村史、民俗等は
各項目の執筆者が所属する長野市誌編さんの専門部会を示しています。
『市誌研究ながの』第11号 A5判 184頁 価格1,400円 平成16年2月発刊
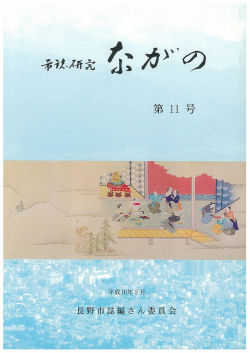
長野市内居館跡調査資料補遺
市川孝之
(原始・古代・中世史)
善光寺周辺の奉納俳額
金井清敏
(近世史)
明和期犀川末流域の洪水と国役普請
滝澤公男
(近世史)
宮崎梅塘の俳句革新運動
- 「新声会」の創設をめぐって -
駒込幸典
(近現代史)
松代青年会のあゆみ
古澤友三郎
(近現代史)
翻刻『お塩亀松口説』
小林一郎
(旧市町村史)
火防祈願の形
- 長野市域の秋葉進行 -
山崎ます美
(民俗)
太平洋戦争と海軍高級参謀富岡定俊少将
高木 寛
(前市誌編さん委員)
長野市域のタンポポの分布
小林規甫
(自然)
『市誌研究ながの』第12号 A5判 214頁 価格1,400円 平成17年2月発刊
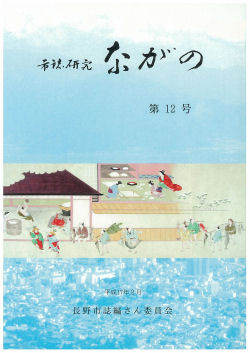
室町・戦国期の新善光寺(その二)
牛山佳幸
(原始・古代・中世史)
中条唯七郎『九州道中日記』を読む
柄木田文明
(近世史)
善光寺用材について
- 佐久郡大日向村用材を中心として -
小金澤敏男
(近世史)
明治初期における村の製糸工場の繰糸鍋について
- 長野県の行政文書史料の分析から -
太田秀保
(近現代史)
校章の制定と寄せる願い
関 秀延
(近現代史)
松代藩「監察日記書抜」・「家老日記」などからみた佐久間象山
長澤 要
(旧市町村史)
藤井伯昌の「旅中日記」
丸田修治
(旧市町村史)
明治初期長野町における懲役場・牢屋の設置経緯とその後の動き
風間 紀
(市誌編さん委員)
長野市内小学校一校制
- 長野県内市町村の小学校一校制との比較において -
宮澤邦典
(市誌編さん委員)
早稲田大学中興の総長田中穂積と人の業績
高木 寛
(前市誌編さん委員)
ジョロウグモの生息密度の季節変化および特筆すべき2種
藤澤庸助
(前市誌編さん委員)
『市誌研究ながの』第13号 A5判 248頁 価格1,300円 平成18年2月発刊
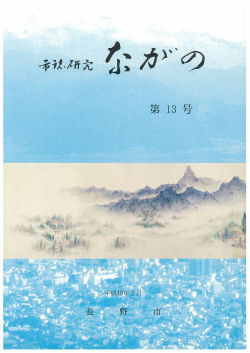
近世における善光寺史関係の著作について
牛山佳幸
天保十五年「諸方御持参薬法控」の紹介(一)
鬼頭康之
善光寺地震二次災害犀川大洪水
岡澤由往
藤井伯昌の「旅中日記」(二)
丸田修治
「小学校令」以後の軍事教育
塩入 隆
松代出身の小説家 松の家みどりとその周辺
関保男
「日露戦役従軍戦誌」(その一)
相澤篤信
第一回国勢調査の長野市の正しい世帯数と人口を求めて
宮澤邦典
製紙王藤原銀次郎の人と業績
高木寛
長野電鉄地下化・長野大通り建設と駅周辺第一土地区画整理事業
山上茂司
『七番日記』にみる女性の生活と北信の民俗
鈴木明子
皆神山のクロサンショウウオの卵嚢数変化
宮澤佳寛
『市誌研究ながの』第14号 A5判 197頁 価格1,200円 平成19年2月発刊
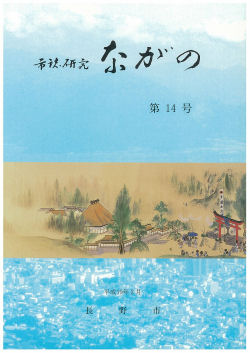
わが国の公文書館制度の現状と長野市公文書館への期待
梅原康嗣
天保十五年「諸方御持参薬法控」の紹介(二)
鬼頭康之
善光寺地震の災害情報
- 読売・摺物を中心に -
降幡浩樹
守礼にみる一農家の幕末?明治にかけての信仰
- 篠ノ井西横田柳澤家の守礼資料 -
細井雄次郎
松代騒動の一端
丸田修治
要路から外れた松代町の交通網整備への努力
古澤友三郎
巣鴨獄中歌にみる人間青木一男
高木 寛
メッセージから読み解く都市民の心情
亀井好恵
富栄養湖 涌池の陸水生物学的研究
- 1 水質と基礎生産 -
落合照雄
『市誌研究ながの』第15号 A4判 164頁 価格1,200円 平成20年2月発刊
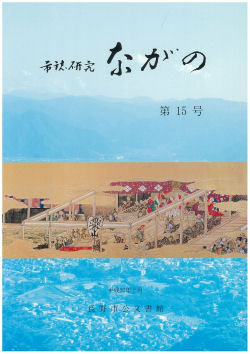
長野市公文書館開館記念講演
記録を守り記憶を伝える
~市民のアーカイブズ(公文書館)をめざして~
安藤正人
最澄の東国伝道と諏訪神
原田和彦
市河文書の着到状と軍忠状について
久保田廣志
松代藩の領内除災御祈祷札配布と雨乞
古川貞雄
渡辺敏と二本松藩の富津台場警衛
西沢安彦
裁判官横田秀雄博士の人と業績
高木 寛
宮田登の民俗学的想像力
阿久津昌三
富栄養湖 涌池の陸水生物学的研究
- 2 水質とプランクトンの経年変化 -
落合照雄
『市誌研究ながの』第16号 A4判 164頁 価格1,300円 平成21年2月発刊
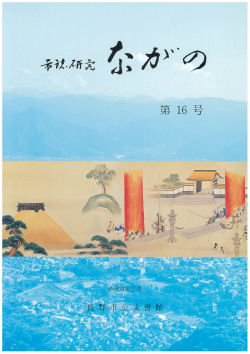
長野市公文書館開館一周年記念講演
平安時代の善光寺をめぐって
- 霊場寺院への発展とその背景 -
牛山佳幸
髻大城と長野県北部の城館遺構
- 横堀遺構に着目した再評価の視点 -
遠藤公洋
上田藩川中島領戸部村の日々
- 「林武夫文書」の紹介 -
鬼頭康之
佐久間象山の漢詩(一)
佐久間方三
悲運の女優松井須磨子の軌跡
高木 寛
島村抱月の英文の詩書 松代清野でみつかる
倉石武一
子どもと社会
倉石忠彦
長野市の都市化とDID人口の動態
山上茂司
『市誌研究ながの』第17号 A4判 168頁 価格1,400円 平成22年2月発刊
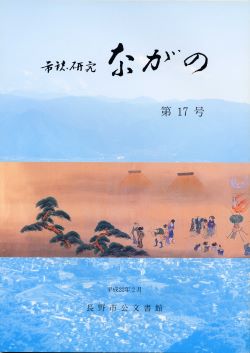
長野市公文書館開館二周年記念講演
真田幸貫と松代藩
- 藩祖顕彰と軍制改革を中心に -
松田之利
水内郡 長沼城の再検討
- 城郭構造を中心として -
河西克造
千曲川中流域における近世末期の治水事業
滝澤公男
天明三年浅間大焼けと凶作
大塚尚三
文化文政期の上人様の御無尽一件について
宮﨑正規
佐久間象山の漢詩(二)
佐久間方三
「御役用日記」の紹介
長野西高校古文書同好会
「江戸日記」の紹介
吉田古文書研究会
新馬喰町日記について
関 保男
松堂丸山弁三郎の人と業績
高木 寛
長野市の桜
落合照雄
再建名号碑と誕生寺正道をめぐって
袖山榮眞
『市誌研究ながの』第18号 A4判 138頁 価格1,400円 平成23年2月発刊
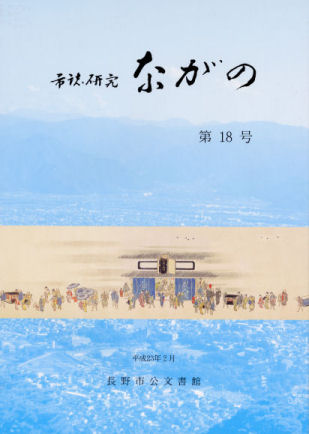
長野市公文書館開館三周年記念講演
松代地域における近代化にかかわる諸相
- 維新期から大日本帝国憲法成立期まで、横田家の人びとの動きを辿りながら -
上条宏之
真田信之文書の基礎的考察
原田和彦
「江戸日記」の紹介(二)
吉田古文書研究会
近世後期における善光寺町の信用事情
- 大本願上人さま無尽講をめぐる試論 -
宮﨑正規
佐久間象山の漢詩(三)
佐久間方三
「御役用日記」の紹介(二)
長野西高校古文書同好会
ある木造校舎の物語
- 信田小学校記念館 -
大屋 弘
「学校資料」について
- 城山小学校資料から考える -
宮澤崇士
作曲家草川信の人と業績
高木 寛
『市誌研究ながの』第19号 A4判 170頁 価格1,400円 平成24年3月発刊
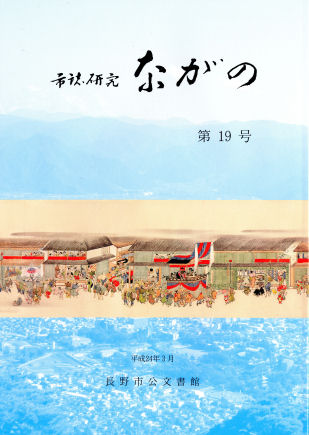
長野市公文書館 開館四周年記念講演
善光寺地震に学ぶ ―震災の特徴と発生メカニズム―
赤羽 貞幸
郷土長池が生んだ高僧規菴祖円(南院国師)と南禅寺
高木 寛
古文書に見る野生鳥獣 ―松代領を中心に―
大橋 昌人
佐久間象山の漢詩(四)
佐久間 方三
弘化四年三月廿五日より五月五日至
「御役用日記」の紹介(三)
―善光寺西町宮下銀兵衛「御役用日記」―
長野西高校古文書同好会
通称「坊主学校」盛衰記 ―焼けた坊主学校の謎解き―
袖山 榮眞
忠魂碑の歴史をみる
―創建・撤去・再建をめぐって―
小林 康男
旧制長野中学校本校舎に関する基礎的建築史研究(一)
―本館校舎移転改築に関わる過程と建築様式名―
宮澤 政太
松代ボーリングコアデータの共有と活用に向けた保存について
伊藤 拓馬
宮澤 崇士
長野市西部地区の池沼と湧泉の水質プランクトン 1
落合 照雄
『市誌研究ながの』第20号 A4判 132頁 価格1,400円 平成25年3月発刊
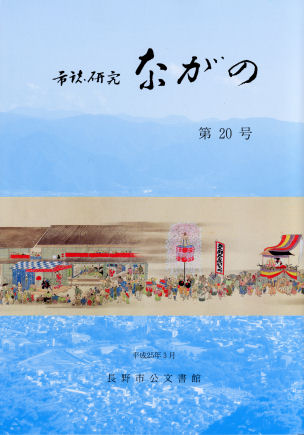
長野市公文書館 開館五周年記念講演
カラスをめぐる風雅 ―芭蕉・蕪村・一茶の世界―
玉城 司
善光寺地震と上田藩川中島領
―更級郡戸部村を中心として―
鬼頭 康之
佐久間象山の漢詩(五)
佐久間 方三
三井物産と長野県製糸業
―一九〇七年における生糸直輸出について―
横山 憲長
旧制長野中学校本校舎に関する基礎的建築史研究(二)
―設計図と設計者、RC造と木造―
宮澤 政太
歌道・茶道に生きた教育者白鳥義千代
高木 寛
資料目録と解説
―平成24年度移管「長野市役所文書」―
宮原 秀世
長野市西部地区の池沼の湧泉の水質とプランクトン 2
落合 照雄
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
- 市誌研究ながの第31号~第32号
- 長野市公文書館-ご購入方法
- 市誌研究ながの 第1号~第10号
- 市誌研究ながの 第11号~第20号
- 市誌研究ながの第21号~第30号
- 長野市誌民俗調査報告書
- 写真は語る
- 戦後70年
- 第1巻自然編
- 第2巻歴史編(原始・古代・中世)
- 第3巻歴史編(近世一)
- 第4巻歴史編(近世二)
- 第5巻歴史編(近代一)
- 第6巻歴史編(近代二)
- 第7巻歴史編(現代)
- 第8巻旧市町村史編(旧上水内郡・旧上高井郡)
- 第9巻旧市町村史編(旧更級郡・旧埴科郡)
- 第10巻民俗編
- 第11巻資料編(自然)
- 第12巻資料編(原始・古代・中世)
- 第13巻資料編(近世) 第14巻資料編(近現代)
- 第15巻総集編 第16巻歴史編(年表)
こちらのページも読まれています